2009年02月28日
なぜ、飽きるのか(1591)

練習ですぐに集中力を切らしてしまう選手がいます。
これは、練習に「飽きた」ということです。
写真を撮るの「飽きる」ことがない写真家の話をしました。
その人は、良い写真を撮るためにそれこそ何時間も待つそうです。
それで、
「大変ではないですか?」
という、インタビューに答えて、
「花に愛情があれば苦にはなりません。」
「その時にしかない花の表情を撮るためには、愛することが何よりも大切です。」
と言っています。
テニスを大好きでいられるかどうかが何よりも大切だということですね。
もちろん、練習は楽しいことだけではありません。
苦しいことのほうが多いに決まっています。
でも、それでも頑張ることができるのは、テニスが好きだからです。
この気持ちが強ければ「飽きる」ことはないですね。
私は何年もテニスを教えてきました。
「飽きる」ことはありません。
それは、写真家の言葉を借りれば、
「その時にしかない子どもたちの輝きを導くために、愛することが何よりも大切です。」
ということです。
すぐに「飽きて」しまう子どもたちには、テニスをもっと好きになってほしいと思います。
好きになれば、どんな時でもトライします。
好きになれば、苦しくても耐えることができます。
好きになれば、ほんの少しのことで感動します。
「飽きる」ことは・・・ありません。
そんな気持ちが高まるように教えていきたいと思います。
2009年02月27日
テニスのフットワーク -10- (1590)

テニスの科学(35)
◎正しいフットワークを身に付けるための4つのステップ
スタンスの研究をすすめてきた中で、今回の研究結果や他の研究結果、ならびに我々の指導経験から総合的に判断して、テニスに必要なフットワークを身に付けるために必要な、いくつかの視点がみえてきました。
それらを「4つのステップ」としてまとめてみました。
「ステップ1:軸足で正しく立つこと」
安定して立ち、ボールを待つということは、正しいタイミングをはかり、安定したスイング動作を生むためには必要不可欠なことです。
その際に、腰を軸足側に捻ることが、安定した待機姿勢を保つためは重要なポイントです。
また、ステップ足は軸足の後方に置き、どの方向へもステップ可能な準備姿勢を整えることが重要です。
「ステップ2:スクエア・スタンスで、かかとから踏み込む」
初心者には、スクエア・スタンスから習得させるのが良いと思います。
なぜなら、回転運動をすみやかに、タイミングよくおこなえない初心者にとって、正しいスイング動作を身に付けるためには、踏み込み足を伴って、並進運動から回転運動のスムースな移行を練習したほうが良いからです。
また、ステップをネット方向に踏み出すことは、インパクトの時間的な誤差が多少許され、適切なインパクトのタイミングを図れない初心者にとって、ボールコントロールを高めるために有利に働きます。
ただし、クローズ・スタンスでの打球は、スムースな回転運動を疎外する可能性もあると考えられるので、導入に際しては避けるべきだと考えます。
そして、つま先からの着地は回転運動を疎外するので決して行わないことに注意してほしいと思います。
「ステップ3:ユニット・ターン」
安定した待機姿勢を作るとともに、強い回転運動を生むために、腰や肩の捻りが必要です。
そのために、テイクバック期に肩と腰を同時に捻ること(ユニットターン)が重要です。
その際に、初級者や中級者は、どうしてもラケットや腕の動きに意識を向けがちであるが、腰に意識をおいておこなうことがポイントです。
また、ラケットを大きく引きすぎると、それだけ迅速な回転動作がおきにくくなるので、軽く肘から引くようにして、コンパクトなテイクバックを心掛けるべきです。
「ステップ4:オープン・スタンスーストローク最終形」
一流選手と同じ様に、オープン・スタンスで打つことは、ストローク動作の目標です。
1から3のステップがほぼクリアできた(すなわち、ユニット・ターンやスムースな回転動作が無意識にできるとともに、適切なインパクトのタイミングを図ることができ、あらゆる方向に移動した場合でも、軸足で正しく安定して立つことができる)なら、できるだけ早期にトライすべきです。
その場合に、自分が「速い」と感じるスピードのボールに対して練習することをすすめます。
なぜなら、オープン・スタンスは、速いボールに対して、素早く対応することができるスタンスであり、できるだけ、短時間にユニットターンをおこない、素早い準備動作と回転動作を身に付けるための練習が必要だからです。
また、コート・カバーリングの素早さも、オープン・スタンスの大きな特徴であるので、テンポ速く左右に打ち出されたボールに対して打球する練習も導入する必要だと思います。
2009年02月26日
クローズアップ(1589)

えっとですね、またまた買ってしまいました!クローズアップレンズです。
何度も言いますが、衝動買いではありません!・・・多分。
実は、これは、レンズと言っていますが、通常のレンズの前にフィルターのようにして装着するタイプのレンズです。
これを着けると、被写体により近づいて撮ることができるので、被写体を大きく写すことができます。
そのような目的のために専用に設計されたマクロレンズと比べてはいけないのかもしれませんが、なかなかのものです。
この前買った、50mm、F1.4の写りが素晴らしいので、このレンズでいろいろなものが撮りたくなりました。
そのままでもいいのですが、これから咲き誇る花たちのいろいろな表情を写し撮りたくなってきます。
かといって、最新のマクロレンズを買うのはちょっと、と考えていたところ、このレンズの存在を知ったわけです。
値段も手ごろで、フィルター感覚で気軽につけて撮ることができるのはいいですね。
早速、いろいろなものを撮ってこようと思いましたが、この時期なかなかいい被写体がないのが悩みです。
でも、このレンズを50mm、F1.4のレンズに着けて、被写体を探し歩いていると、今まで気にも留めなかったものに心惹かれたりします。
頭の中に、クローズアップされた被写体をイメージしているので、いつもと同じような場所であっても観る感覚が違います。
ある花の写真家が、
「飽きることなどありません。花はいつも違う表情を見せてくれます。その表情を写し撮ることだけを考えていれば、同じような写真はありません。」
というようなことを言っていました。
人間は日常化してくると、いつも同じと「錯覚」してきます。
それは、自分自身の観点が留まっている証なのかもしれませんね。
レンズを変えれば観る目は変わる・・・。
時々自分のレンズを変えて、観る目を変えていかなくてはいかないのかもしれません。
2009年02月25日
テニスのフットワーク -9- (1588)

テニスの科学(34)
◎ユニット・ターン
身体の捻りとスタンスは大きな関係があると述べました。
そこで、動作解析の結果から、特に、腰と肩の捻りについてみてみることにします。
各スタンスにおける肩関節と腰関節の角度変位を調べました。
肩関節角度は、両肩を結んだ線とネットのなす角度、腰関節角度は両腰を結んだ線とネットのなす角度で、両角度とも上方からみた角度です。
まず、角度変位に着目してみると、上級者は、インパクト直前まで肩関節角度と腰関節角度に大きな差はみられません。
それに対して、初級者と中級者は、肩関節角度は大きな変位を示しているものの、腰関節角度の変位が小さいことがわかりました。
このことは、上級者は、インパクト直前まで、肩も腰も同じ様に十分に捻っているのに対して、初級者、中級者は、腰の捻りが十分でないことを示しています。
特に、初級者のオープンでは、肩関節角度の変位が小さく(肩を十分に捻っている)なっているのに対して、腰関節角度は変位変動がほとんどない(腰を十分に捻っていない)ことが示されました。
初心者は、身体の捻り(特に、腰の捻り)が少なく、ネットに正対してインパクトを迎えることが多く観察されるとの報告もあり、この結果は、これらの報告と一致します。
安定したスイング動作のためには、軸足で正しく立つことが重要であると述べましたが、片足で安定して立つためには、腰をわずかに外側に捻る(軸足側に捻るといった方が良いかもしれない)ほうが良いと思われます。
上級者は安定した待機姿勢を保つために、腰の捻りを行っていると考えられます。
それに対して初級者、中級者は腰の捻りが十分でないので、安定して立つことができません。
特に、オープンでは、両足をネットに対して平行に近い形でスイング動作を行うので、腰を十分に捻ることができない初級者、中級者は、軸足に正しく立つことができないのです。
また、安定した待機姿勢を作るとともに、強い回転運動を生むために、腰の捻りが重要になってくるのは当然のことです。
そのためには、肩と腰を同時に捻る必要があります。
これは、ユニット・ターンやボディ・ターンといわれるもので、その重要性は多くのコーチが指摘しており、ジャック・グロッペル博士も、その研究データからユニット・ターンの重要性を指摘しています。
次に、角速度についてみると、上級者は、インパクト直前からインパクトにかけて、肩関節角速度が急激に増加し、増加の途中でインパクトを迎えています。
それに対して、初級者と中級者の肩関節角速度は、インパクト直前にピークがあり、速度が衰えながらインパクトを迎えていることが示されています。
初級者と中級者では、腰の捻りが十分でなく、また、腰の回転のパワーを肩の回転のパワーに結び付けることができないと考えられます。
2009年02月24日
声が出ない(1587)

打ち込みなどの練習で、打つ時に「声が出ない(声を出さない)」選手がいます。
できるだけ強いショットを打つことが目的の練習なので、全力で打とうとすれば、自然と「声は出る(息を強く吐く)」ものですが、それができません。
疲労による筋力低下を観察する実験で、筋力が低下してきた時に大きな声を出すと筋力が一時的に高まることが報告されています。
これは「シャウトの効果」として知られています。
「ここぞ!」という時に、強い力を出すために「声」は大変大切であることを示しています。
強いショットを打つために声を出して全力で打とうとすると、かえって力んでしまってうまくいかないのではないか、と思われるかもしれませんが、「声を出す」ことでそれをうまく調整しています。
声が出せずに、息が詰まった状態で大きな力を出そうとすると、力みが大きくなってスイングのバランスを崩します。
そういう選手は、うまく自分のテンションを上げられず、マイナスの身体表現を取ることも多いので、持っている力をうまく引き出せないことが多いですね。
「ガッツポーズができない」と書きましたが、それは「ここ」からつながっています。
私は以前、トップ選手の試合中の行動について調べたことがあります。
そのすべての選手が大切なポイントでは声を出して打ち、ポイントを取った時にはガッツポーズなどの行動を取っていました。
その行動には個人差がありますが、多かれ少なかれ、行動の変容はあるわけです。
私はテニスという競技の特性を考えれば、このような行動を取ることが適正だと考えています。
戦いの場面では、緊張した時でもいかに自分の力を出し切れるか、ということが勝敗を決めます。
そのための訓練として、「声を出す」ことはとても効果が高いと思います。
昨日の練習でも、そう注意をして練習をさせた選手がとても良いショットを打っていました。
「このショットが打てればトップ選手になることも夢ではない」と感じさせるものです。
そんな雰囲気を作り出すための必須のアイテム、それが「声を出す」ことなのかも知れません。
これからも、スポーツ選手として、その力を最大限に引き出して戦うことができるように、いろいろと工夫しながら教えていこうと思っています。
2009年02月23日
ガッツポーズができない理由(1586)

よく、子どもたちに「なんでガッツポーズできないの?」と聞くことがあります。
素晴らしいショットを決めても下を向いたり、無表情な子どもたちの多いことに驚きます。
私たちコーチは、そんな時、
「自分の気持ちを高めることができないで、どうして勝つことができるんだ!」
と叱咤することもあります。
そんな時、剣道ではガッツポーズをとると一本が取り消しになるという話を思い出しました。
また、あるコラムに
「技を掛けた時に審判を見る事や、勝った時に大袈裟にガッツポーズをする事は単に「ポイント制スポーツ」としての柔道ではよろしく、...しかし、「武道」としての柔道、つまり嘉納先生が世界に広めたかった「日本の心」を伝承するものとして僕は認めたくありませんね。
理由はちゃんと説明できますよ。
まず簡単な理由。
技が決まった時、相手を投げた時、...その時相手は既に死んでいますか?...。
たとえポイントが決まっても、試合が終わっても、もしも相手が「参っていなかったら」、反撃してきたらどうしますか?。
これを武道では広く「残心」と言い、真剣で切り捨て、倒れた相手にでも気を抜かず、刀で低い構えを倒れた相手に取って、随分長い間これを維持します。
我が流派ではこれを「下段霞崩し」の構えで行います。
次に、武道での勝ち負けは一喜一憂するものではありません。
礼節を重んじます。
勝者は敗者に対し、心を一つにして精一杯戦った相手への礼儀として笑ったり喜んだりしません。
これが謙虚と言う事です。
今時分は相撲でも勝って笑う力士がいますが、日本の文化はもう既になくなっているのかも知れませんね。
ま、今一番こういった日本的精神世界を感じるのはイチローくらいですか。」
と書いてありました。
多くの子どもたちが、
「ガッツポーズを取る」ことができないのは、
実は薄れてきたとはいえ、「武士道の精神が文化的に身体に刻み込まれているのかもしれない」、
などと考えていましたが、
どうも最近の子どもたちが「ガッツポーズできない」のは、こういう日本伝統の武士道精神的に考察するものではないようです。
もし、武士道精神が薄れ揺らいでいるのなら、もっと派手にガッツポーズする子どもたちが増えてきてもおかしくありません。
これは社会的な構造変化に深く関係しています。
ここでは詳しくは書きませんが、武士道精神とはあまり関係ないことだけははっきりしています。
また、対人スポーツであるが、接触スポーツではないテニスでは、頭にきて相手をどついたり、蹴り飛ばすような行為は、ネットが邪魔でできないので(もししたらそれはそれですごいことかも)、その精神的な安定を、自分のいる場所にしか求めることができません。
なので、声を出し、ガッツポーズをするなど自分の気持ちを鼓舞する行為が必要となります。
マサイ族のダンスのようなものかも・・・。
もちろん、イチローのように、そして宮本武蔵のようにより高い精神構造を身につけることが究極的な目標かもしれませんが、まずは、勝つために自分の気持ちを高めることを訓練したほうがよさそうです。
しかし、
「礼節を重んじます。勝者は敗者に対し、心を一つにして精一杯戦った相手への礼儀として笑ったり喜んだりしません。これが謙虚と言う事です。」
ということだけは忘れないようにしてほしいものです。
これを忘れると、単なる、「自己中」で「わがままで」、ついでに「アホ」な奴といわれてしまうので注意してください。
ガッツポーズは、冷静に、自分に向かって、謙虚に行うのが日本人的かもしれませんね。
2009年02月22日
テニスのフットワーク -8- (1585)

テニスの科学(33)
◎踏み込み足はかかとから
次に、スタンスの違いがインパクト位置にどう影響するのかに興味を持ちました。
スタンスが違えば、当然、インパクト位置にも違いがあらわれるであろうと考えたからです。
インパクト位置をみると、初級者は、中級者と上級者とは明らかに違いがあることが示されています。
中級者と上級者は、各スタンスにおけるインパクト位置に違いがないのに対して、初級者は、ばらつきがみられ、インパクト位置が身体に近いことがわかります。
テニスのフォアハンド・ストロークでは、体に対する足の位置や、前足の向きがボールの方向を決めるという報告があります。
また、この初級者は踏み込み足のつま先が内側(時計の正方向)に屈曲されたまま、かつ、つま先から着地してスイング動作を行うことが観察されています。
つま先を屈曲したまま着地することは、腰の回転を制限することになり、並進運動の次に行われる回転運動がスムースに行われなくなります。
そのために、初級者では左右腰の角度がネットに対して、直角に近くなり、インパクト位置が身体に近くなったのです。
踏み込み足のつま先を内側に屈曲させたまま、つま先から着地して打球してみてください。
身体の回転がスムースに行われず、非常に窮屈な感じで打たなければならないことがわかると思います。
また、一流選手が踏み込んで打っている写真をみればわかりますが、ほとんどの場合、つま先の内側への屈曲は行われず、つま先ではなくかかとから踏み込んで打っています。
それによって次の回転運動をリズミカルに、スムースに行うことができるのです。
2009年02月21日
テニスのフットワーク -7- (1584)

テニスの科学(32)
◎タイミングを正しく合わせるためには、安定して立つこと
オープンスタンスは、インパクトのタイミングを合わせるのが難しいスタンスである、と書きましが、インパクトのタイミングについて、左右足の着地からインパクトまでの時間と、膝関節の角度変位の分析データを参考にしながら考察をすすめてみます。
スタンディング・ショットについて、各スタンスにおける左右足の着地からインパクトまでの時間を調べました
このデータをみると、技術レベルがあがるにつれて、右足(つまり軸足)の着地からインパクトまでの時間が全体的に長くなっていることがわかります。
これは、何を意味しているのかというと、上級者ほど、軸足で長く安定して立てるということです。
このことを確認するために、膝関節の角度変位の分析結果をみてみます。
右膝の角度変位をインパクトまでをしらべました。
これをみると、特に初級者については、オープンにおける角度変位の様相が、クローズとスクエアに比べて異なっていることがわかります。
正のピーク値(山の尖がり)の現れるのがインパクトに近く、その立ちあがりも急です。
つまり、急激に膝の屈伸運動を行っているのです。
中級者は、変位の幅は大きい(膝を大きく曲げ伸ばししている)ものの、膝の曲げ伸ばしが緩やかであり、スタンスによる違いはあまりみられません。
また、上級者は、すべてのスタンスにおいて、インパクト直前までの変位が少なく、約130度で推移しています。
初級者と、中級者が大きな変位を示したのとは対照的です。
上級者は、右足の着地が早いにもかかわらず、その変動が少なく、非常に安定して立っていることがうかがえます。
安定して立ち、ボールを待つということは、正しいタイミングをはかり、安定したスイング動作を生むためには必要不可欠なことです。
上級者は、そのための身体の動きや調整力を身に付けていると考えて良いと思います。
しかしながら、そのように訓練された上級者であっても、ランニングショットにおける、オープンでの打球では、コントロールにばらつきがみられます。
また、右足着地から左足着地までの時間も、右足着地からインパクトまでの時間も、オープンが最も短かかったです。
オープンは、踏み込む時間を節約して、すぐに回転動作に結び付けるための技術なので、軸足のセッティングもステップ動作の切り替えも素早く行われなければなりません。
このことからわかるように、オープンスタンスはそれなりに難しい技術であるといえます。
しかし、オープンスタンスはスイングのターン時間(全スイング動作にかかる時間)もリターン時間(走り出して、打球し、もとのポジションまで戻る時間)もクローズに比べて短いこと、また、相手の速い打球に対して、身体の捻りを大きくとらなくても打球することが可能であるなど、上級者が高いレベルでの試合に勝つためには、習得しなければならない技術であることは明白です。
どの段階で、どのような練習に取り組むのかというヒントが必要です。
また、上級者のクローズにおいて、インパクトに向かって右膝が屈曲していくという、他のスタンスと違う動作がみられます。
これは、踏み込み幅の大きいクローズにおいては、上半身が前のめりにならないように右足を左足の方向に寄せて、スムースな回転動作が行われるように調整していると考えられます。
踏み込み幅が大きい場合に、安定した回転動作、スイング動作を行うために必要なことなのかもしれません。
2009年02月20日
RAW(1583)

RAWというのは、「〈ものが〉原料のままの, 未加工の, 精製してない 」と意味です。
写真の分野では、撮像素子のデータを加工しないで、そのままのデータを記録することをいいます。
そうして記録したデータを後で加工して現像し、一枚の写真に仕上げていきます。
どんなメリットがあるのかというと、ホワイトバランスなどを後でどうにでも設定できるというのはそのひとつです。
ホワイトバランスとは、
基本的に写真撮影を行う際、フィルムカメラにおいては、大抵の場合、フィルムは日中の太陽光(デーライト)の色温度にあわせて作られている。
そのため、電球や蛍光灯のような人工の光、また太陽光でも曇天時や早朝においても色温度が変化するため、正確な色が出なくなる。
これはデジタルカメラにおいても同様で、適正な色温度が設定されていない場合、正確な色が出ない。
むしろデジタルカメラの方がはっきり影響が出る傾向にある。
こうした状況で色を正確に出すために、一定の色基準(純粋な白色もしくは18パーセントグレー)を基にして、デジタルカメラ内蔵の画像処理プロセッサ(画像エンジン)が判断し、適正な色を出すようにする機能がホワイトバランス機能である。
ということで、これが後で現像する時に設定可能になって、いろいろな雰囲気の写真を作ることができます。
もちろん、色合いやシャープネス、コントラストなどもできる限り元のデータを劣化させることなく変更することができます。
初めの頃は、「写真なんて見れればいいじゃん」と思っていたので、JPEGといって、後で加工しなくてもそのままで見ることができる形式でしか撮っていませんでした。
後で現像するという手間をかける必要はないと思っていました。
しかし、自分が撮った写真をより美しく見せたり、自分の印象のままに再現するには、このRAWデータを現像する方がメリットが大きいわけです。
そう考えて、最近ではRAWで撮ることが多くなりました。
確かに現像は面倒ですが、美しく仕上がってくる写真を見ることのほうが楽しみは大きいですね。
そんな時に、スポーツの指導もまさしくそうだなと思いました。
撮った写真の構図などは変えられません。
しかし、いろいろと手を加えることで、その写真が最も美しく見えるようにすることはできるのです。
持っている資質を変えることはできなくても、子どもたちの才能がもっとも輝くことができるように手を加えることはできます。
それがコーチの仕事なのかもしれません。
もちろん、最後は自分の力で羽ばたきますが、その手助けをうまくやってあげることができれば、きっと輝けるはずです。
そんな作業は根気のいる仕事ですが、根の気があれば必ず良いものができるという自信はあります。
そんなことを気付かせてくれる写真はやぱっりいいなあと思います。
より機能的なグラフィックソフトがほしくなってきました。
あぶない、あぶない・・・。
2009年02月19日
テニスのフットワーク -6- (1582)

テニスの科学(31)
◎ボールの打球コースに差がある
各スタンスにおけるボール打球コースをみると、特徴的な傾向がみられます。
まず、スタンディング・ショットについて、初級者と中級者のオープンスタンスでは、左コース(被験者は全員右利きです)に打球される割合が高く、約40%が打球されています。
テニスのストローク動作は、並進(直線)運動と回転運動から構成されます。
この並進(直線)運動は、体に勢いを持たせるとともに、続く回転運動をリズミカルに行うための導入的役割を担います。
また、ラケット面を打球したい方向へ長く移動させることができるので、インパクトの誤差が少なくなります。
オープンスタンスでは、スクエアスタンスやクローズスタンスに比べて、打球したい方向に足を踏み込まないために、身体の並進(直線)運動が少なく、回転運動が主な身体動作になります。
そのために、上級者に比べて、インパクトのタイミングを適切に合わせることができない初級者と中級者では、左コースに多く打球されたのだと考えられます。
特に、スタンディング・ショットでは、身体の移動を伴わないために、その傾向が顕著に現れました。
ランニング・ショットについて、上級者でもオープンスタンスにおけるコースのばらつきが顕著でした。
オープンスタンスは、上級者であっても、移動して、タイミングを適切に合わせるのが困難であることを示しています。
オープンスタンスはインパクトのタイミングを合わせるのが難しいスタンスであると言えます。
2009年02月18日
涙を流す(1581)

ある新聞のコラムに、
「たまっているストレスを一気に解消してくれる<秘密兵器>もある。それは、何と『涙』で、特に感動による号泣が有効だという。」
と、「脳からストレスを消す技術」という本の内容を紹介しています。
試合で負ける、うまくプレーができない、など、スポーツはストレスが多いものです。
よく泣く子がいますが、そうやって「感情の浄化」のできる子は「ストレスに強い」ということができるのかもしれません。
ある曲の歌詞に、「涙の数だけ強くなれるよ」というのがあります。
他にも、涙を流すことで精神的に強くなると歌ったものは多いですね。
だから、感情を抑え込むのではなく、うまく感情を出すことができるような雰囲気を作ってあげる必要があります。
「大島コーチと話をしていると泣けてくる」と言われたことが何度かあります。
そういう雰囲気が作れているのかもしれません。
大切なことは、ストレスをためないこと、うまく付き合っていく、ということです。
また、「涙は女の武器」と言われることもあります。
人を陥れるために使われるのはかないませんが、ストレスに対する武器として使うのであれば良いのではないでしょうか。
まあ、いつの時代でも、男性は女性の涙には弱いものです・・・ね。
2009年02月17日
テニスのフットワーク -5- (1580)

テニスの科学(30)
◎スタンスの違いによるボールコントロール得点に差はない
各スタンスにおけるボールコントロール得点の結果をみると、初級者において、すべてのスタンスで、ランニング・ショットよりもスタンディング・ショットの得点が高い傾向が若干みられるほかは、特徴的な傾向を読み取ることはできません。
スタンディング・ショットよりもランニング・ショットの方が高いフットワークの能力が要求されるのは当然のことであり、初級者ではランニング・ショットに対するフットワークの能力が備わっていないということができます。
しかし、スタンスの違いによる差は見い出すことはできません。
中級者と上級者は、どのスタンスで打球したとしても、ボールコントロールにそれほど差はないのに対して、初級者ではスクエアとクローズのほうが、オープンに比べて高い得点を示すと予想していたので、この結果は意外でした。
この結果をみる限り、スタンスが違ってもボールコントロールには差はないということができます。
しかし、得点だけでは、ボールコントロールを評価することができないと考え、ボールの打球コースを調べてみることにしました。
2009年02月16日
道具を大切にする(1579)

良いカメラやレンズを買うと、何だか嬉しくなっていつでも持ち歩き、気が向いたらシャッターを押しています。
もちろん、練習にも持って行って、子どもたちの表情やスイングを撮ったりしています(さすがにレッスン中に撮ることはありませんが・・・)。
この前、試合にも持って行きましたが、見る試合がたくさんあるとなかなか写真を撮る余裕はないですね。
そして、写真を撮った時には、家に戻ってきて写真の整理やカメラのメンテナンスをします。
カメラやレンズについたほこりをブロワーという道具で吹いたり、液晶ビュー画面の汚れを丁寧に拭いたりします。
結構面倒ですが、これがまた楽しいのです。
よく考えてみると、私たちがテニスを始めたころは、みなラケットなどの道具をとても大切にしていたように思います。
木のラケットだったので、雨で湿気ると反ったりしますので、ちゃんとカバーを付け、中に乾燥剤などを入れていました。
何本か持つようになると、反りを防ぐ木の枠でできたプレスにラケットを挟んで持ち歩いていました。
私がこだわったのはグリップです。
人差し指にグリップテープの溝がうまく当たるように、何度も何度もグリップテープを巻き直します。
当時は、今のように優れたオーバーグリップなどないので、革巻きのグリップを丁寧に巻き直しながら使っていました。
また、グリッパーという道具があって、これはグリップの部分だけがある道具ですが、ちゃんと市販されていました。
でも、あまりお金がなかったので、使わなくなったラケットのグリップを切り落とし、それに同じようにグリップテープを巻いて授業中も握っていましたね(授業は聞いていたような、聞いてなかったような・・・聞かないでください!)。
そうやって道具を大事にすることを覚えていったと思います。
今は、良いものが何でも揃います。
小さな子どもでも何本ものラケットを持ち、颯爽とプレーします。
そのプレーに魅了されることは多いですが、試合の後、乱暴にラケットをしまい込んだり、バッグの中が煩雑だったり、グリップがぐちゃぐちゃに巻かれているのをまったく気にせずに使っていたりするのを見ると、もうちょっと丁寧に扱ってほしいなと思います。
イチロー選手は、自分の道具は自分でメンテナンスするそうです。
「自分の感覚は自分でしかわからないので、ちゃんと自分でやらなければならない」と言っていました。
こういう「感性」は大切ですね。
毎年、多くの子どもたちを連れて海外などに遠征に出ます。
その時、初めに言うのは「自己管理」です。
自分の持ち物をちゃんと自分で管理することは言うに及ばず、早めに睡眠をとる、ちゃんとストレッチする、怪我があればケアをして、試合前には十分に力を発揮できるようにアップをする。
こうした一連のことをしっかりとできる選手になるということです。
その「感性」を磨くためにもっとも大切なことが、「道具を大切にする」ということなのだと思います。
今日も何枚か撮ってきました。
なかなか良い写真を撮ることは難しいですが、「感性」を磨くためにちゃんと道具の管理をしようと思います。
2009年02月15日
20年(1578)

今読んでいる本に、
「自分のコーチングが成功したかどうかは20年たってみないとわからない。
選手たちがやがて年齢を重ね、人間的に豊かに成長を遂げたことが明らかになったときにこそ、初めてそのコーチは競技場の内でも外でも、『真の勝者』としての評価をあたえられるのだから」
と、書いてあります。
コーチとしての成功は、競技の成績で決まるものではない、ということを明確に示しています。
昨今のテニス界を騒がす事件には大変残念な思いでいます。
競技の成果を求めすぎた結果なのかもしれません。
自分のコーチとしての評価は良く分かりません。
でも、自分の仕事が子どもたちの人間性の向上に寄与するものであったのなら、これ以上の喜びはありません。
あと8年で20年になります。
どんな評価を与えられようとも、その喜びのために一生懸命に仕事しようと思っています。
2009年02月14日
テニスのフットワーク -4- (1577)

テニスの科学(29)
世界のトッププレーヤーとして数々の実績を残したマイケル・チャンという選手がいます。
テニスプレーヤーにしては小柄で、体格的に劣るマイケル・チャンが世界のトッププレーヤーでいることができたのは、その類まれな精神力もさることながら、フットワークの良さを指摘する者は多い。
福井烈元デ杯監督は、「軸がぶれない」、「上半身がぶれないので、安定した打球ができる」と、マイケル・チャンのフットワークに対して高い評価をしていました。
フットワークが良いとはどういうことでしょうか。
いくつか考えられますが、まず、足が速いこと、そして、ストップ、ターン動作をスムースに、タイミングよく行うことができること、バランスよく立つことができ、回転動作をスムースに行うことができること、などが挙げられると思います。
そのためには、それらの技能を習得するための特別なトレーニングや練習が必要であることはいうまでもありません。
しかし、テニスは「足ニス」といわれるように、フットワークの重要性は他のスポーツに比べて高いにもかかわらず、その指導法は確立されているとはいいがたく、指導書の解説と一流プレーヤーのフットワーク、特にフォアハンド・ストロークにおけるスタンスには大きな違いがあることがわかりました。
そこで、今回は、コントロールテストならびに3次元動作解析の結果についてみてみることにします。
●テスト概要
一流プレーヤーと、指導書において推奨するスタンスでは、フォアハンド・ストロークにおいて異なることがわかりました。
では、一般プレーヤー、特に初級プレーヤーにはスクエア・スタンスが本当に良いのでしょうか?
その疑問に対して、コントロールテストと動作分析を試みました。
実験に参加したのは、初級者2名、中級者2名、上級者1名の計5名で、スタンディング・ショットとランニング・ショットにおけるテストを実施しました。
スタンディング・ショットでは、ベースライン中央に立ち、、前方から打ち出されるボールに対して、各スタンス(スクエア、クローズ、オープン)をとるように、それぞれ10球連続して打球しました。
ランニング・ショットでは、シングルス・サイドラインとベースラインの交点をスタート地点として、前方からボールが打球された後スタートし、ベースライン中央付近で各スタンスをとるように、それぞれ10球連続して打球しました。
その際、被験者の側方および前方からビデオ撮影を行い、スイング動作を記録しました。
反対側のコート上には、AからYまでの25のエリアを設定し、ボールバウンド地点を記録し、ボールコントロールの指標としました。
なお、被験者には、ある特定のエリアをねらって打球するように指示しました。
そして、記録されたビデオから3次元座標値を算出し、動作分析を行いました。
今回分析をおこなった項目は、
1.各スタンスにおけるボールコントロール得点
2.各スタンスにおけるボール打球コース
3.左右足着地からインパクトまでの時間
4.右膝の角度変位
5.インパクト位置
6.肩関節角度、腰関節角度の角度変位と角速度
以上の項目です。
結果と考察につい打ては次回に報告します。
2009年02月13日
テニスのフットワーク -3- (1576)

テニスの科学(28)
一般のプレーヤーにおいては、指導書を頼りにすれば、前述のようにフォアハンドストロークではスクエアかクローズ、バックハンドストロークではクローズが良いということになります。
それでは、一流プレーヤーは、どのようなスタンスで打っているのでしょうか。
もちろん技術レベルが違うので、一般のプレーヤーに比べてスタンスの出現頻度が異なるであろうことは容易に想像できますが、一流プレーヤーも一般プレーヤーと同じようにフォアハンドではスクエアやクローズが多く、バックハンドではクローズが多いのか、また、各スタンスの出現頻度はどれくらいなのかは非常に興味が湧くところです。
そこで、一流プレーヤーのゲーム中における各スタンスの出現頻度を調べることにしました。
調査したのは、調査時点での世界ランキング第1位のプレーヤー男女各1名で、対ストローカーと対ネットプレーヤーとの対戦について、それぞれ調査しました。
調査方法は、試合途中10ゲームのグランドストローク全ショットについて、その打球時点でのスタンスを1つづ記録していくという、大変原始的で根気のいる方法を選びました。
それが最も有効な方法です(でも、本当に大変な仕事です)。
そして、記録した全ショットをフォアハンドストローク、バックハンドストローク、フォアハンドリターン、バックハンドリターンの4項目に分け、それぞれの各スタンスの出現頻度を確認しました。
ビデオ分析の結果について、特徴的な点をまとめてみます。
1.フォアハンドはオープン
フォアハンドについては、ストローク、リターンともにオープンで打球する場合が圧倒的に多く、70%から80%の割合を示しています。
特に、女子プレーヤーのフォアハンドリターンについては89%と、ほとんどのショットをオープンで打球していることが示されています。
フォアハンドではスクエアかクローズが良いとする一般の指導書とはまったく異なります。
一流選手は違うのだ!といってしまえばそれまでですが、では、どこがどう違い、一般プレーヤーはいつから、一流プレーヤーのように打つ練習をすればよいのかという課題が残ります。
2.バックハンドストロークはクローズ
バックハンドストロークについては、男女のプレーヤーに共通して、対ストローカーではクローズが約50%と最も高い割合を示し、対ネットプレーヤーでは約80%と相当高い値を示しています。
バックハンドストロークについて、クローズの割合が高いことは、指導書で述べられていることと一致し、指導書の解説は正しいことになります。
では、相手プレーヤーのプレースタイルによって、バックハンドストロークにおけるスタンスの出現頻度が変わる、つまり、対ネットプレーヤーではクローズの割合が増えるのはなぜでしょうか。
ネットプレーヤーは、ネット付近で攻撃することが多く、それだけ角度を付けてショットすることが可能である(ワイドに攻撃できると言っても良い)。
そして、そのようなワイドに攻撃されたショットに対しては、当然、カバーする範囲が広くなり、遠位のボールに対して打球しなければならない機会は多くなるはずです。
その場合、バックハンドでは、ラケットを持つ手から遠いほうの打球を処理するために、踏み込み足を打球方向に大きく踏み出すことによって、身体の捻りを大きくする必要があります。
そのために、クローズが多くなると推測されます。
つまり、バックハンドでクローズが多いのは、利き手と反対側での打球に際して、身体の捻りを大きくする必要があるということです。
逆に、フォアハンドでは、身体を大きく捻る必要がさほどなく、そのためにオープンが多用されるのかもしれません。
どうも、身体の捻りとスタンスは密接な関係がありそうです。
3.バックハンドリターンは、オープン
バックハンドリターンでは、ストロークに比べて、オープンで打球する割合が増大しています。
特に男子プレーヤーでは、対ストローカーと対ネットプレーヤーでのバックハンドストロークにおけるオープンの割合は、それぞれ10%、16%なのに対して、バックハンドリターンでは55%、61%と、約40%もその割合が高くなっています。
女子のプレーヤーについても、バックハンドリターンでは、ストロークに比べてクローズの割合が減り、オープンとスクエアの割合が増えています。
2の結果について、バックハンドでは大きな身体の捻りが重要で、そのためにクローズが多くなるのであろうと推測しましたが、身体を大きく捻るためには、それだけ時間がかかります。
現代のスピードテニスでは、サービスは最も大きな武器であり、そのスピードは時速200kmを優に超えます。
そのために、身体を捻る十分な時間が無いと考えることができます。
その証拠に、サービススピードの速い男子プレーヤーの方が、リターンにおけるオープンの割合の増大が著しい傾向がみられます。
以上のことをまとめると、次のようになります。
1.フォアハンドでは、オープンが圧倒的に多く、バックハンドではクローズが多い。
2.バックハンドでは、ストロークとリターンではスタンスの出現の割合が大きく異なる。
3.身体の捻りと、相手のショットのスピードがスタンスに大きな影響を与える。
2009年02月12日
新しい仲間?(1575)

昨日は午後の練習がなかったので、久しぶりに家族で出かけました。
午後からの日帰りなのでそう遠くへはいけませんが、イルミネーションで有名な「なばなの里」へ行くことにしました。
ここはガーデニングも有名なので、新しく買ったレンズや以前買った望遠レンスなどを持って、重いバックを担いでさえも出かける気持ちが高まってきます。
せっかくなので、子どもたちにもそれぞれカメラを持たせ、いろいろな角度から花や風景を撮るように言いました。
まあ、これは自分がゆっくりと写真を撮るための策でしたが、子どもたちは喜々として何枚も何枚も写真を撮っていました。
今回はイルミネーションがメインで、しかも夕方からは時折小雨が降る薄暗い雰囲気の中での撮影だったので、ちょっと難しかったかもしれませんね。
でも、子どもたちがカメラを片手に必死になって写真を撮っている姿を見ると楽しくなってきます。
カミさんからは「写真を撮っている姿が一緒!」と大笑いされました。
なかなか出かける機会もないので、写真を撮ることに興味を持ってくれて、「一緒に出かけよう!」と言ってくれることを期待したいと思います。
なんだか新しい仲間(?)が増えたみたいで嬉しくなってきます。
そうなると、子どもたちのために良いレンズを買わなくてはいけないかもしれません。
どんなレンズにしようか、今から考えていこうと思います。
えっ、もちろん、自分のでは・・・ありません・・・よ。
た・ぶ・ん・・・・。
2009年02月11日
テニスのフットワーク -2- (1574)

テニスの科学(27)
研究を進めるに当たって、
1.指導書を調査し、スタンスに関する記述の内容を整理すること。
2.一流プレーヤーのビデオ分析を行い、各スタンスの出現頻度を調べること。
※各スタンスとは、
●スクエア・スタンスー両足がサイドラインと平行なスタンス
●クローズ・スタンスー両足がサイドラインに対してクローズなスタンス
●オープン・スタンスー両足がネットと平行に近いスタンス
3.初心者、初級者、上級者のボールコントロールテストを行い、スタンスおよびレベルの違いがボールコントロールにどのように影響するのかを調べること。
4.各スタンスで打球中の3次元動作分析(特に足と腰の動きを中心)を行い、その特徴と技術レベルとの関係を把握すること。
を研究目標にしました。
「指導書の調査」
スタンスに関する研究の第1歩として、現在市販されている指導書および月刊誌、ビデオなどを詳細に調査し、その内容を検討することにしました。
調査した指導書の中から、テニスのフットワーク、特にスタンスに関する記述のあるものをピックアップし、内容を整理しました。
フットワークに関する記述は少ないのですが、それにも増してスタンスに関する記述は少ないというのが現状です。
スタンスに関する記述のあるものは、調査した50冊中の22冊で、半分以下です。
1.フォアハンドストロークについて
フォアハンドストロークについてみると、スクエア・スタンス(以下、スクエア)が良いとするものが7冊と最も多く、次いでクローズ・スタンス(以下、クローズ)が良いとするものが4冊で、この2つを合わせると、スタンスに関する記述のある指導書(22冊)の中で50%になります。
また、初級者について、クローズが良いとするもの、スクエアが良いとするもの、オープンが良いとするものがそれぞれ一冊づつあり、もし、それらの指導書を総て読んだ初級プレーヤーがいたなら、そのプレーヤーはどのスタンスを選ぶのでしょうか?
その他にも、ボールとの距離によってスタンスを使い分ける、という解説もありますが、プレーの中で瞬時にして距離を判断し、スタンスを選択するのは至難の業でなないでしょうか。
ここら辺りにも、フットワークやスタンスに関する指導の混迷を垣間見ることができます。
2.バックハンドストロークについて
続いて、バックハンドストロークについてみると、クローズが良いとするものが9冊と最も多く、次いでスクエアが良いとするものが4冊となっています。
バックハンドストロークのスタンスに関する記述のある指導書は、フォアハンドストロークに比べると少ないので、スクエアとクローズで70%以上を占めます。
その他に、フォアハンドストローク、バックハンドストロークともに「状況に応じて」という解説がありますが、どのような状況なのかについては詳細な説明はありません。
以上の結果からいうと、フォアハンドストロークではスクエアかクローズ、バックハンドストロークではクローズが良いということになります。
私たちの指導経験でも、フォアハンドストロークについてはスクエアがよく、バックハンドストロークについてはクローズが良いと指導する場合が多いので、予想通りの結果といえるでしょう。
しかし、そのことが必ずしも正しくないことは後でわかります。
2009年02月10日
衝動(1573)

えっとですねえ、またまた買ってしまいました。
そう、レンズです!
50mmのF1.4の単焦点レンズです。
明るいレンズがほしくて、いろいろと調べていたところ、ある本屋で手にしたカメラ雑誌のレンズ大賞に輝くこのレンズがどうしてもほしくなり、衝動買いです。
今日、そのレンズが届きました。
朝から何枚も試写しまくりです。
リサイズしていない写真を掲載できないのがちょっと悔しいです(泣)。
今までのレンズに比べて、ボケの美しさがあって、対象が浮き出る感じはとても良いと思います。
この焦点距離のレンズ(ズーム)はもちろん持っていますが、描写の違いは歴然ですね。
初めてカメラを買った頃は、たくさんのレンズを買い求めてしまう、いわゆる”レンズ沼”に落ちることはないだろうと思っていました。
今はどっぷりはまっています(笑)。
なぜなんだろう、とちょっと考えてみました。
まずは、もっと良い写真を撮りたいという至極当然の欲求があります。
同じ焦点距離をカバーするレンズでも、解放値などによって映りはまったく違います。
写したい対象を撮るのにもっとも適したレンズがあるので、できればそれで撮りたいわけです。
最近は、高倍率ズームの良いレンズがありますので、大半はそれでまかなえてしまいますが、それに慣れてくるとちょっと物足りないところも出てきます。
それをカバーするのが、明るい単焦点レンズであったり、小さなものを大きく写せるマクロレンズだったりします。
それを使い分けて写し、その描写の違いに酔いしれるのは結構気持ちの良いものです。
もうひとつは、たくさんレンズを持っているという満足感です。
自分がこれだけ写真を撮ってきた、という歴史のようなものを感じるんですね。
もちろん、すべてのレンズを同等に枚数を重ねてきたわけではありませんが、それぞれに撮った時の思い出はあるわけです。
それを重ねることで、写真やカメラに対する「思い」も深まっていきます。
その「思い」を続けるためにも、新しいレンズを買う、という衝動的な行為が必要なのです(言い訳っぽいかも)。
衝動買いというと、なんだか計画性もない、浪費の代表のようなイメージがありますが、「これだ!」という「衝動」がある、ということはとても大切だと思います。
もちろん、何でもかんでもというわけにはいきませんので、「衝動」が大きければ大きいほど、その「衝動」を我慢する忍耐力もつくということです。
そして、何よりも、感性はその都度磨かれていくということです。
レンズが変われば、撮りたい対象が変わるだけではなく、カメラアングルや、ポジションも変わり、今までとは違う視点でものを見ることができるようになります。
スポーツの指導者は、そういう感性で子どもたちの可能性を探ります。
ひとつの見方、やり方ではうまくとらえることが難しいですね。
そんなことを写真を撮ることから学んでいます(えらい!)。
多くの読者の方は、「たんなる衝動買いじゃん!」と思っているかもしれませんが、そうではないんです!と強調しておきます。
では、またまた今からカメラを持ってお出かけしてきます。
ああ、忙しい!
2009年02月10日
テニスのフットワーク -1- (1572)

テニスの科学(26)
テニスは「足二ス」といわれるように、昔からテニスにおけるフットワークの重要性は指摘されてきました。
テニスは移動範囲が大きい(ネットを隔てて対峙するスポーツの中では、最もコート面積が広い)ばかりでなく、急激なターン動作や俊敏な動きが要求されるために、ほかのスポーツに比べてフットワークの重要性はより高いと思われます。
特に近代テニスは、スピードテニスへと進化(道具やボールの改良は大いに関係があります)し、スイングスピードもさることながら、フットワークのスピードがより重要になってきました。
「フットワークが良いから、スイング動作が安定している。」
「フットワークの良いものは、リズムが乱れない」
など、フットワークの善し悪しが、プレーに大きな影響を及ぼすことを示す記述や解説は、多く目にするところであり、ストロークのミスの70%は、ストロークの打ち方自体ではなく、動きやバランスの悪さが原因であると指摘する研究者もいます。
これらのことから、「フットワークの善し悪しがテニスの勝敗を左右する」と断言してもよいと思います。
しかし、前述の会話のように、実際にテニスを指導する際には、フットワークの指導はあまり行われず、適切な指導書も少ないのが現状ではないでしょうか。
フットワークを指導する場合でも、確固たる自信があるわけではなく、なんとなく今までの練習方法を踏襲してきたに過ぎません。
テニスのフットワークは、単に走る動作だけをいうのではなく、準備姿勢、準備動作、テークバック、移動、停止、スタンス、スイング動作、リターンで構成されます。
そこで、これらの構成要素の中で、フットワークとして最初に習うであろうスタンスについて調査・実験し、フットワークの指導体系の確立に向けての第1歩を踏み出すことにしました。
その内容について、解説します。
コーチのみならず、ウィークエンド・プレーヤーにおいてもフットワークは大きな課題であり、少しでも役に立てればと思っています。
2009年02月09日
冬場のウォーミングアップ(1571)

寒い時に一番気になるのは怪我や体調を壊すことです。
せっかく一生懸命練習してきても、怪我や体調不良で試合に負けてしまうのがもっとも残念です。
コーチも、その点に関しては最大の注意を払いますが、毎回すべてを監督することはむつかしいので、各自でできるだけ管理をしてください。
冬場のウォーミングアップとトレーニングに関する注意点をロングウッドジュニアテニスアカデミーのホームページに載せておきましたので目を通しておいてください。
ウォーミングアップの基本的な考え方は、
①筋温を高める
②筋肉の柔軟性を高める
③関節の可動域を高める
④筋反応を高める
(そのスポーツ動作に多い運動要素を取り入れて、筋肉のその運動に対する反応を高めるように準備をする)
⑤全力の筋力発揮に対する耐性を高める
などを、できるだけ短時間にできるように工夫することです。
選手の特性は考慮する必要がありますが、基本的な考え方に違いはありません。
もちろん、寒いときほど長く入念にウォーミングアップを行うことは当然のことです。
私が、個人的にプロ選手のウォーミングアップを行う場合は、少なくとも30分は時間をとります。
そして、ウォーミングアップの基本的な考え方にのっとり、その選手の特性で、どの要素を重点的にアップするのかを考えながら指導します。
テニス選手は、筋持久力に優れている人が多いので、ある程度長い時間をウォーミングアップにかけても大丈夫な場合が多いです。
よく、「長い時間ウォーミングアップをすると疲れるから」ということを言う選手がいますが、そういう選手はぎりぎりの勝負で勝つことはむつかしいと思います。
最後の最後は体力が勝負を分けます。
ウォーミングアップで疲れるような体力では絶対に勝つことはできません。
逆にウォーミングアップである程度追い込むことで体が楽に動くようになるくらいの選手でないと、上の世界では戦えないのです。
みんなはそこを目指して、トレーニングやウォーミングアップで手を抜かないような選手であってほしいと思います。
2009年02月08日
気の元?(1570)

東海毎日ジュニアの愛知県予選が行われました。
いくつかの会場を見てきましたが、そこで感じることは、なんだか「元気」がない、ということです。
この大会は全国選抜ジュニアの予選もかねているので、大変大切な大会ですが、それを勝ち抜く「迫力」のようなものが乏しいようにも感じます。
今のジュニア選手を取り巻く育成の環境では、声を上げたり、感情を出したり、私たちの時代ではあたりまえにやられていたことができにくい状況にあることは理解できます。
でも、しかし・・・、テニスといえども勝負事です。
相手に勝つために自分のできることはがむしゃらにやる(もちろんルールやモラルの範囲内で)ことができなくては、勝負事に勝つことはむつかしいだろうと思います。
かといって、経験を重ねてきて、今の行動パターンが作られてきているので、それをすぐに変えることはむつかしいだろうから、せめて「元気」よく試合をしてほしいと思うのです。
「元気」は気の元です。
ここで、「気」は、やる気、勇気、負けん気などでしょうか。
どれも「勝つ」ためには必要なことに違いありません。
その「元」がなくては何も出てはこないだろう、と思うのです。
だからとりあえず、元気!元気!、この姿勢で臨んでほしいと思います。
私もみんなに負けないぐらい元気にレッスンするぞ!っと、あっ、腰が.....、肩が......、やっぱそっといたわりながらやらないかんわな。
2009年02月07日
テニスはどうすれば上手くなる -4- (1569)
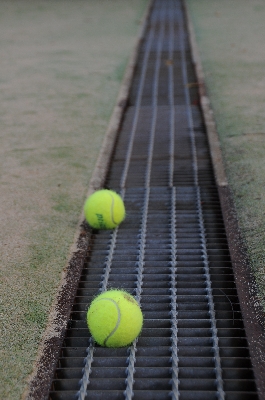
テニスの科学(25)
さて、もう一つの障壁の「特異性」についてですが、これは簡単に言えば、そのスポーツの独特の動きを意識してトレーニングしなければ効果はないという理論です。
例えば、サービスの動作を向上させようとして、上腕三頭筋や大胸筋などの筋肉を個別にトレーニングしていくだけでは実際のサービスは速くなりません。
サービス動作を行う中に負荷をかけるとかして、その運動形態にあったトレーニングしなければならないのです。
このように、スポーツにはそのスポーツ独特の動きの「妙」があって、これを意識してトレーニングや練習を行わなければなりません。
これが結構くせものです。
それを体験したのが、私のバッティングの経験です。
実は、野球の指導を行っている際に、マシンでバッティングを行える機会を得ました。
その昔(いったい何年前でしょうか?)、野球少年であった私の心をくすぐり、密かな自信とともにバッターボックスに立ちました。
それまでスイング動作などを指導していたし、自分のスイングを鏡などで見たり、選手・監督にチェックを受けてかなりいい評価を得ていました。
しかし、飛んでくるボールを打っている自分の姿(動作分析のためにビデオを撮影していた)を見て愕然としました。
「こりゃーテニスのスイングだ!」
これが紛れも無い私の印象です。
ただバットを振っているときには、いっぱしの野球選手(?)である私が、実際にボールを打つということに意識を奪われるとテニス選手に戻ってしまうのです。
同じように「打つ」という形態のスポーツであるにもかかわらず、私の脳に組み込まれたプログラムはまさしく「テニス」なのです。
これが「特異性」です。
やはり、テニスはテニスのトレーニングを行わなくてはなりません。
今までは色々な運動を行わせることが良いとされてきましたが、ある時期からはその運動を専門的に行わせるべきだと思います。
運動プログラムが出来上がってくる7歳から11歳頃までにそのスポーツを十分に経験し、トレーニングを行うことが良いと考えています。
野球など、比較的類似性の強いスポーツならまだ良いかもしれませんが、やはりテニス選手を目指すなら、テニスを十分に経験させるべきです。
いくつかテニスが上手くなるにはどうしたら良いかについて私の考えを述べてきました。
その考えを整理しておきます。
素振りをする
簡単な練習から行う
練習やトレーニング方法を工夫する
やる気が大事
身体意識を高める
筋感覚を伴うイメージトレーニングを行う
色々なトレーニングをバランス良く組みあわせる
オンコートでのトレーニングを習慣化する
テニスの特徴的な動きをトレーニングする
早い時機にテニス専門の練習・トレーニングを行う
常にテニスの動きを意識してトレーニングを行う
知識を蓄える
項目別に整理すればこのような内容になります。
これには専門の研究者からは異論もあるかと思いますが、私なりに「科学的な知識を蓄積したきた」結果至った結論です。
参考になれば幸いです。
2009年02月06日
ミスの重さ(1568)

スポーツに限らず、何にでもミスはつきものです。
しかし、同じような状況でミスをしてもその「重さ」には差があります。
大切なポイントでミスをすれば大きく心が揺らぎます。
相手のマッチポイントであれば、それで試合終了となります。
ポイントの重要性がミスの「重さ」と深く関係している、というのはこういうことです。
でも、もっと大切なことは、自分が作り出してしまう「重さ」があるということです。
ポイントの重要性は、自分で作り出したのではなく、ポイントを積み重ねていって、たまたまそういう状況になったということです。
これは自分ではどうしようもないところです。
そうではない、ミスの「重さ」を作り出してしまうもの、とは何でしょうか。
それは「過信」です。
多くの人は気づいていないかもしれません。
この間、試合の後に泣いた選手がいます。
試合の結果は「勝ち」です。
でも、悔しくて泣いてしまいます。
ここに「ヒント」があります。
なぜ、その選手が泣いたのかというと、「自分のプレーができなかった」ということです。
対戦した選手は、自分よりちょっと実力的には劣ると思われる選手です。
多分、自分もそう思っていました。
でも、思わぬ攻勢にあい、焦り、自分のプレーを見失ってしまったということです。
そういう時の「ミス」は、とても「重く」心にのしかかります。
その「重さ」に耐えかねて、うなだれたり、苦痛の表情をしたり、だらだら歩いたり、などのマイナスの身体表現が多くなります。
それが、また「重さ」を増やして、自分自身を縛っていることに気がつかないでプレーをしてしまいます。
うまくいくはずはないですね。
「ここ」が、本当の意味での、選手としてのメンタリティーが試されるところです。
その前の日、レベルの高い選手と試合をしました。
試合の結果は完敗です。
でも、試合の後は晴れ晴れとした表情をしています。
プラスの身体表現が多く、気迫も感じられ、「自分のプレーができた」と話してくれました。
試合の結果ではなく、その試合にどういう姿勢で臨んだのかによってこうした差が生まれます。
前の日の試合は、まさしく「チャレンジャー」だったということです。
ミスを恐れず、果敢に攻めていって敗れた。
でも、攻めていく姿勢を持って挑んでいたので、ミスをしても前向きな気持ちなることができ、自分のプレーをし続けることができた、ということです。
でも、泣いてしまった試合では、負けるはずがない、完璧にたたきのめすことができる、という「過信」が、ひとつのミスの「重さ」を大きくしてしまい、まったく自分のプレーができなかったということです。
人間は、「意識」の持ち方ひとつでこれだけプレーが変わります。
同じ状況で生まれたミスであっても、「意識」の持ち方でまったく違う意味(「重さ」)を持つということです。
では、どうすれば良いのかというと、「チャンレジャー」になることです。
「チャンレンジャー」は謙虚です。
攻める気持ちを高く持っています。
負けても相手の実力を認めることができます。
そういう気持で戦えば、ミスは「重く」はありません。
成長のための経験になります。
試合の後、そんなことを話しました。
ミスを「重く」してしまう、「過信」をすることなく、常にチャレンジャーでいる選手に成長してほしいと思います。
2009年02月05日
素直さ(1567)

選手が大きく伸びる時、その選手は「素直に」いろいろなことを受け取る「感性」が高くなっていると思います。
世界記録でオリンピック2冠を達成した北島選手が、前回オリンピックの後国内戦で敗れ、「素直に」自分の過信を認めました。
そして、その後、コーチに「一から始める」と宣言し、大変「素直な」気持ちで練習に取り組んだことが書かれているのを読んだことがあります。
***************************
いくらコーチが優れていようとも、その解決法が有効だとしても、その効果には大きな差があります。
その差は「純粋性」にあります。
人間は、他人の意見に従うことを本質的には苦手としています。
「自分のことは自分しかわからない」、という至極当然の思いを強く持っています。
だから、うまく人に意見を求めるのが苦手です。
でも、自分の力を伸ばす人の特徴は、「素直に人の意見を聞くことができる」ということです。
依存するのではありません。
自分の意見を確固として持ちながらも柔軟に対応できる力を持っているということです。
***************************
と書きました。
「純粋性」は、「素直さ」と同義です。
「素直さ」は、人の心を柔軟にします。
「素直さ」は、やる気を高めます。
「素直さ」は、苦しさに耐える力を高めます。
「素直さ」は、周りのすべてのものを力にかえることができます。
「素直さ」は、そんな強さを持っています。
「素直さ」は・・・強くなるための武器です。
そんな「強さ」を身につけてほしいと思います。
2009年02月04日
テニスはどうすれば上手くなる -3- (1566)

テニスの科学(24)
「トレーニング」という言葉が出てきました。
トレーニングの必要性は誰もが認識しています。
しかし、いざ行おうとすると難しいものです。
それはいくつかの壁があるからです。
まずは、「意識」の問題です。
トレーニングは「嫌なもの」です。
「嫌なもの」を無理にやっても効果はあまり期待できません。
「やる気」でトレーニングの効果は大きく変化することは知られています。
だから、この「やる気」をまずもって高めることがトレーニングになります。
これには工夫がいります。
私の行っている工夫は、まずは道具です。
人間は、道具があるとやる気が出るものです。
道具には合理性を感じさせるし、より効率的にトレーニングを行うことができるように工夫を重ねた歴史が道具にはあります。
そのような道具を使うことはもちろん良いのですが、私は、手作りのバランスボードや安い家庭用のトレーニング機器を利用するように心がけています。
このような道具でも、工夫さえあれば立派にトレーニングの機器として活用できます。
しかし、「やる気」が高まってもまだこれで解決というわけにはいきません。
あと3つも壁があるのです。
これがまた厄介です。
その3つとは、「多様性」と「特異性」、そして「環境」です。
「多様性」とは、そのスポーツのパフォーマンスを向上させるには、多くの運動要素をトレーニングしなければならないという理論です。
運動要素とは、筋力やパワー、持久力やスピード、敏捷性、バランスなど、それこそ無数にあります。
それらを全部トレーニングしろといっても、無理ですね。
だから、どうしてもトレーナーの得意な分野のトレーニングに偏る傾向があります。
筋力主義者は筋力トレーニングばかり行うようになります。
このようなトレーニングの偏りは、テニスのようなボールゲームには大変に危険です。
間違えば、パフォーマンスの向上どころか、低下させることにもなってしまいます。
ひとつのトレーニングにとらわれずに多くの運動要素をトレー二ングしなければならないのは科学的にも正しい事実なのです。
そうなると、バランス良くプログラムを組まなくてはいけませんが、多くの知識が要求されるし、「環境」が整っていない場合には、それに合わせてプログラムを組み直すことも要求されます。
私が指導しているある運動クラブのトレーニングメニューは450種目以上にもなります。
これでは普通のコーチではお手上げです。
そこで、私はコーチにはテニスの動きを向上させるオンコートでのトレーニングから始めるように薦めています。
テニスでは、捻りや切り返し、急激な停止などの運動形態が多いですね。
それらの運動を取り出して、その動きがバランス良く行うことができるようにトレーニングを工夫することです。
2009年02月03日
節分(1565)

今日は節分ということで、コートで豆まきをしました(いいんかな?)。
もちろん、鬼は私です(白水コーチも鬼をやらされました)。
子どもたちは容赦がありません。
こっちも本気で(?)襲いかかります。
こうしたコミュニケーションはとても大切ですね。
そのためには、大人も童心にかえって、こころから楽しむことだと思います。
ほんのわずかな時間でしたが、とても楽しい時間を過ごしました。
コートに散らばった豆を拾い上げてはほうばる子どもたちを見ていると、最近の子どもたちの中ではたくましいほうに入るんだろうなあ、と妙に感心してしまいます。
そのたくましさを大きく育んでほしいですね。
ところで「節分」とは何でしょうか。
ちょっと気になったので、調べてみました。
「節分(せつぶん、またはせちぶん)は、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。節分とは「季節を分ける」ことをも意味している。」
ということらしいです。
ふうん、という感じですが、それに関連する豆まきについて書いてある内容を見て「おっ」と思うことがありました。
「父親などがそれをかぶって鬼の役を演じて豆撒きを盛り上げる。しかし元来は家長たる父親が鬼を追い払うことで権威を示すものであった。そのため父親が鬼の役をするのは間違いともいえる。」
えっ、そうなの?という感じですね。
今日の豆まきは、私が鬼でした。
家に帰って、家の子どもたちとも豆まきをしましたが、私が鬼です。
今までもずっとそうでした。
家では、もちろん私がお父さんです。
コートでは、私が家長たる存在です。
その私が鬼をやることは間違いなのです!
良いことを知りました。
来年は、そのことをきちんと伝えて、私が鬼を追い払おうと思います。
2009年02月02日
テニスはどうすれば上手くなる -2- (1564)

テニスの科学(23)
いくらこの基本的な練習が重要であることが理解できたとしても、民間のテニススクールで「素振り」を導入することは難しいと思います。
私も一般の方を対象としたスクールを受け持っていますが、素振りなどは行いません。
それは、1球でも多くボールを打ちたいという皆さんの要望に応えなくてはいけないという思いと、時間的な制約があるからです。
しかし、できるだけ優しい練習から行うほうが良いことは間違いないので、練習のはじめは、「手」でできるだけ優しいボールを投げて、それを打つから練習するようにしています。
いきなりネット越しにボールを送球することは避けていただきたいと思いますが……まわりのレッスンがそうでないとなかなか導入しにくいかもしれませんね。
また、 レッスンの導入にしてもそうですが、優しい技術から導入するようにしています。
ストロークよりはボレーの方が、対応という点から考えても優しいはずです。
小さな子どもに打球させてみると、ボレーのようにノーバウンドで打つ方がはるかにうまく打ちます。
これは、ボールの飛行軌跡の情報処理がワンバウンドのボールを打つよりもやさしいからです。
やさしいボールを打つことから始める方が、身体感覚をチェックすることもやさしいので、導入としてはこの方が良いと思います。
もちろん、ジュニアの選手育成コースでは素振りの練習を、トレーニングとして位置づけて行っています。
2009年02月01日
ラリーボール(1563)

ラリー練習について、
******************************************************
大切なことは速いボールを打つことではありません。
自分が確実にコントロールできるボールのレベルを上げることです。
そのためには自分のベースを確認して練習をする必要があります。
それが「ラリー練習」です。
******************************************************
と、書きました。
その通りなのですが、なかなか「自分のペース」で、というのが難しいですね。
ラリーをただ続けるだけであれば何球でも続けることができる、ということだけでは実践では通用しません。
ショットの威力の弱い低年齢の時であれば、それだけで勝ち上がることはできますが、その次のレベルにステップアップする時にそうした「クセ」が大きな壁になることもあります。
「ラリーボール」とは、「相手に攻撃されないショット」であることを理解して練習することです。
ボールのスピードが遅くても、回転が強かったり、弾まないスライスボールであったり、深いロブだったり、相手の苦手なコースだったり、攻撃されないショットはいくつもあります。
トッププロであっても、そうしたボールを配球しながら、ウイニングショットを打つチャンスを作ります。
ラリーの能力が高ければ、自分が攻撃する機会がより多くなるので試合を有利に進めることができます。
その力をつけてほしいと思います。
また、半面のラリー練習では中途半端なフットワークしか使わない選手がいます。
ただボールを打っているだけでは良い「ラリーボール」は打てません。
たとえ半面でもしっかりと動いて、自分の一番うまく打てるポイントできちんと打ってくる(打とうとする)選手のボールにはプレッシャーを受けます。
同じボールでも、そうした動きによってボールは威力を持つ、ということを忘れてはいけません。
ラリー練習とウォーミングアップのラリーのボールが変わらない選手は多いものです。
それは、こうした「意識」が低いということです。
強くなるためには、どうすれば自分の有利な展開を作ることができるか、それを一心に考えて練習しなければなりません。
そのために一番基本となるラリーを高い意識を持って練習してほしいと思います。













